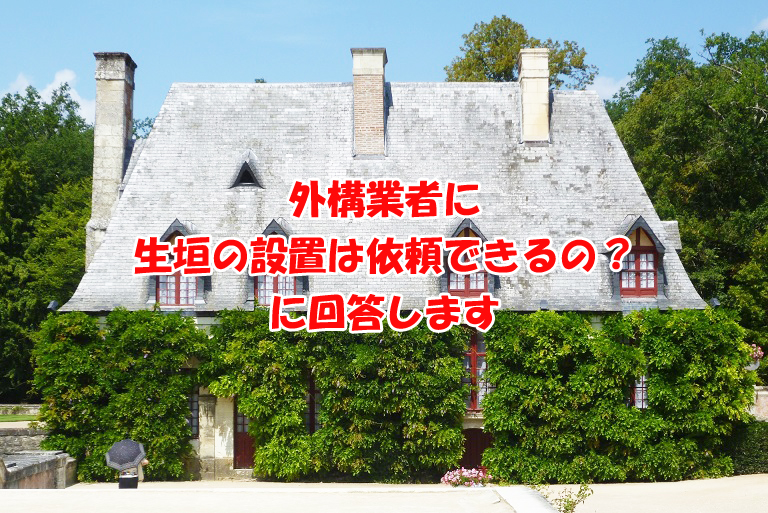外構業者に敷地の境界に目隠しを依頼したいけど、生垣を選択することもできるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
生垣は敷地の区切りや目隠しをより自然な形で行うことができ、フェンスや塀など他の目隠しの方法よりも圧迫感が少ないことで人気を集めています。
外構業者が生垣の設置をしてくれれば、他の外構工事と一緒に進めることができ、他の業者に依頼する手間や時間を節約することもできますよね。
また、敷地全体のデザイン性を統一できるという面でも、外構業者に生垣の設置を依頼できれば、安心して任せることができるのではないでしょうか。
今回は外構業者に生垣の設置を依頼できるのかという疑問に回答しつつ、生垣の設置に関しての基本的な知識についてご紹介していきます。
【こちらの関連記事もご覧ください】
////外構業者に生垣の設置は依頼できます

生垣の設置は外構業者に依頼することができます。
敷地の区切りや目隠しをする場合、フェンスや塀などの選択肢がありますが、それらと同様に生垣も外構工事の一環として行えます。
ナチュラルな雰囲気を持つ敷地をイメージしている場合、生垣であれば境界の区切りとしても目隠しにもすることができ、フェンスや塀などとは違い自然さや柔らかさをデザインすることができるでしょう。
また、フェンスや塀と生垣を組み合わせることもできるので、費用やデザイン性、メンテナンスなど将来的なことも含めて外構業者に相談してみることをおススメします。
////生垣を設置するメリット

敷地の境界を区切るために生垣を検討中という方に、生垣のメリットについてご紹介しておきます。
生垣を設置することで、フェンスや塀とは違う利点を得ることができます。
生垣で自然な目隠しができる
生垣は境界の区切りや目隠しをより自然な景観で行うことができます。樹木の葉や枝はランダムに生長するので、場所によってさまざまな見え方になります。
フェンスや壁のように規律正しく見えるのではなく、自由で自然な印象でしっかりと刈り込まれた生垣でも柔らかさを感じることができるでしょう。
葉や枝の多さや密度によっても目隠しのレベルが変わりますが、生垣は程よい抜け感のある目隠しとして機能します。
生垣は設計の自由度が高い
生垣は選択する樹木や剪定の仕方や頻度によって、高さや形状、見た目の美しさなどを変えることができます。
フェンスや塀は一度設置すればその高さやデザインが変わることがありませんが、生垣は必要に応じて変化させることもできるなど自由度の高さを持っています。
また生垣はフェンスや塀、他の樹木などとの組み合わせにより、さまざまなデザインをもたせることができ、好みの見た目や機能性を持たせることもできます。
刈り込みの量や手間を減らしたい場合はフェンスや塀と組み合わせたり、グリーンの多いよりナチュラルな敷地にしたい場合は生垣を背景に低木を配置したりするのもいいでしょう。
生垣で景観を良くすることができる
生垣はグリーンにできる面積が広く存在感もあるため、手入れされたものは住宅や敷地の景観だけでなく、地域の景観も向上させることができます。
葉が茂ることで壁を作る生垣の雰囲気は、フェンスや塀には出せない柔らかさを持っています。
境界の区切りや目隠しを整然とした雰囲気にしたくない、自然で柔らかい雰囲気にしたいという場合には生垣を取り入れるのがいいでしょう。
////生垣に向いている樹木とは

生垣に使用する樹木は、基本的に列植しやすいように生産されている生垣用のものを選びます。
他のものではだめということはありませんが、生垣の場合均等に植栽をするため、樹形が1本幹で左右均等の枝という生垣用の植木のほうがバランスのいい仕上がりにできるからです。
また、生垣に向いている樹木というものもあります。
以下の特徴にいくつか当てはまるものがあれば生垣に向いている樹木です。
葉の落ちない常緑樹
生垣には葉の落ちる落葉樹を植えてはいけないということはありませんが、落葉する時期には落ち葉の掃除が必要になります。
常緑樹であれば落ち葉の掃除をする手間がなく、落ち葉が飛散して近隣の迷惑になってしまうということもありません。
季節を感じられる落葉樹は魅力的ですが、落ち葉の処理や近隣トラブルなどが気になる場合には常緑樹の生垣にするのがいいでしょう。
生長がある程度緩やかな樹木
生垣はグリーンの壁を作るためにある程度の生長力が必要ですが、強すぎると将来的に刈り込みがしづらくなってしまうこともあります。
樹木の強さは生垣に必要なポイントではありますが、刈り込みなどの定期的なメンテナンスのことを考えて樹木を選ぶほうがいいでしょう。
刈り込みにも耐えられる丈夫な樹木
生垣は定期的に刈り込むことで、機能的なサイズや見た目の美しさを維持していくことができます。
刈り込みでは幹だけでなく葉も一緒に刈り込むため、これに耐えられる強さを持った丈夫な樹木である必要があります。
葉がよく茂り高密度な樹木
生垣を目隠しとして機能させる場合には、葉が小さくて多い高密度な樹木にします。
緑の壁にすることや視線を遮りたい場合にはこの条件が必要ですが、境界の区切りだったりある程度の抜け感がほしいという場合には密度は気にしなくてもいいでしょう。
病害虫に強い樹木
生垣は病気や害虫に対するメンテナンスも必要になります。
葉の状態や害虫がついていないかチェックしたり、予防や駆除をしたりと定期的に気にかけてあげる必要があります。
生垣の樹木に病気や害虫に強いものを選ぶことで、そういった手間をかけずにすみます。
【こちらの関連記事もご覧ください】
生垣におススメの樹木6種

ここからは生垣の雰囲気を高めてくれるおススメの樹木について見ていきましょう。好みのものや用途に合うものがあればチェックしておきましょう。
トキワマンサク
生垣としてやシンボルツリーとして人気を集めているトキワマンサクは紅花種と白花種があり小さな葉と数多く咲く花が印象的な樹木です。
5月に開花する花は鮮やかな紅色の紅花トキワマンサクと白いバラのような花をさかせるのが白花トキワマンサクです。
常緑樹ですが紅花トキワマンサクは秋になると紅葉した古い葉を落とします。病気や害虫もなく育てやすい樹木ですが、花終わりの花弁などの掃除をする必要があります。
ツツジ
水やりなどの必要もなく紫色の花を咲かせるオオムラツツジは、強さがあり公園樹や街路樹として植栽されています。
刈り込みにも強く、低木から育てるため骨組みが必要ないという特徴があります。
オオムラツツジを生垣にする場合、高くするために同じ程度の幅が必要になるため、生長をみこした設置が必要になります。
ツバキ
耐陰性のあるヤブツバキは内側の葉もよく茂り、大きめの葉ではありますが高密度な生垣を作ることができる樹木です。
高さも出すことができ、4mほどの生垣を作ることもできます。
美しい花が咲きますが、咲き終わりにはそのまままるごと落ちてしまうので、掃除をする必要が出てきます。
害虫のチャドクガがつくこともあるため、農薬散布が必要になりますが、剪定とあわせて業者に依頼するといいでしょう。
マサキ
洋風の生垣に合うのが明るい葉色をもつ斑入りマサキです。縦にのびていく習性があり、密度はありませんが程よい抜け感を得ることができます。
寒さによって葉が落ちることもありますが、春に新芽が出て新しい葉に入れ替わります。
マサキの枝は柔らかく、刈り込みもスムーズに行うことができます。成長期に刈り込みを行っておくと葉の密度を濃く育てることができます。
イヌマキ
生垣の密度や強さが気になるという場合はイヌマキやラカンマキがおススメです。イヌマキは強さがあり、植え付けたあとも健康に根付いてくれます。
イヌマキは通常のものは葉の形状が大きく、生垣には細葉性のものを使用することで密度を高められます。
ラカンマキは小さい葉を持ち枝分かれも細かく多いことから、密度の高い生垣を作ることができます。
季節によって葉を落とすことも少なく、年間を通してグリーンを楽しむことができます。
シラカシ
昔から防風林や防火林として使われてきたシラカシは、フェンスや塀よりも高い位置の生垣を作ることもできます。
高さを求める場合、高所の刈り込みを業者に依頼するための管理費用を考えておく必要があります。
外構業者に生垣を依頼する際の費用

外構業者に敷地の生垣を依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのかご紹介します。
また、生垣を設置する際に自治体によっては助成金が交付されます。生垣助成金に関してもあわせて見ていきましょう。
生垣の設置にかかる費用相場
生垣に使用する樹木は高さや種類によっても異なりますが、およそ1mあたり一万円ほどかかります。
これに作業費や骨組みの材料代、土代、土の搬出費など諸経費がプラスされます。
他に外構工事がある場合などには、安くできる可能性もあるので、外構業者に問い合わせしてみましょう。
生垣の助成金について確認する
生垣の設置をすると、自治体によっては条件付きで助成金を交付してくれる制度を持っています。
また、現在設置してある塀を取り壊すための助成金というものもあるので、塀を撤去して生垣を新たに作る場合には自治体のホームページなどで確認してみましょう。
生垣助成金は多くの場合1mあたりの単価で出されることになります。
生垣助成金を受けるには必要条件があるので、考えている生垣が条件をクリアできるのかということもチェックしてみましょう。
生垣助成金が交付されるまでの流れ
生垣助成金を受けるためには「工事の前に申請する」必要があります。
助成金申請の流れは自治体によっても異なりますが、交付までの例をご紹介します。
1.自治体に相談する
生垣助成金の制度の説明や必要書類、生垣の設置場所の確認日の決定をしに自治体の窓口へ向かいます。
2.生垣の設置場所を確認
自治体の窓口で決めた設置場所の確認日に自治体が撮影や計測を行い、助成金制度を受けることができるか確認を行います。
3.外構業者に見積もり依頼
生垣助成金制度に申請可能であることが確認できたら、外構業者に見積もりを依頼します。
設置場所や制度の条件などは事前に伝えておくといいでしょう。
4.生垣助成金を正式に申請する
外構業者の見積書や図面ができたら、必要書類と一緒に自治体へ提出して助成金の申請をします。
5.決定通知を待つ
生垣助成金の申請から決定通知が来たら、外構業者に生垣工事をはじめてもらいましょう。
決定通知が届く前に工事が進行してしまったり、申請した内容と異なる工事になってしまわないように注意しましょう。
6.生垣の設置が完了したことを報告
生垣の完成写真や工事の完了届、自治体によっては助成金交付を請求するための書類も提出する必要があります。
不備がなければ生垣助成金が指定口座に交付されます。
生垣のメンテナンスにかかる費用

生垣は刈り込みを行うことで、機能性を持ったサイズや見た目の美しさを保つことができます。
刈り込みは自分ですることもできますが、背の高い生垣であったり、刈り込みの時間をさくことができない、きれいな形にしたいという場合には業者に依頼するようにしましょう。
生垣の刈り込みを業者に依頼した場合、2mまでの高さで横1mあたり2000円から3000円ほどが相場です。
これに刈り取った枝葉を処分するための費用がプラスされます。
生垣の設置で気をつけておきたいポイント

生垣は自由度も高く設置場所に関してもある程度の自由度がありますが、メンテナンスが定期的に必要ということを意識しておくようにしましょう。
例えば隣地の境界線に生垣を設置したいという場合には、刈り込みを行う際に隣の敷地に入って作業しなければいけません。
生垣を設置する前に隣の家に刈り込みの際に入る許可をもらっておいたり、50cmほどのスペースをセットバックとしてとって生垣を設置するなどの対策をしましょう。
また、花を咲かせる樹木や落葉する樹木の場合には、花は葉が落ちる季節には定期的に掃除をする意識が必要です。
落ち葉や害虫などはトラブルになるケースもあるので、生垣の手入れをこまめにして近隣の理解が得られるようにしておきましょう。
まとめ
外構業者に生垣の設置を依頼することで打ち合わせなどを一元化することができ、手間や時間を無駄にかけずに設置までの流れをスムーズに進めていけます。
また、他の外構を依頼している場合であれば、デザイン面での統一性なども相談することができるでしょう。
生垣は生きている樹木を使用するため、生長とともに刈り込みなどのメンテナンスが必要になります。
生垣を維持していくために必要な手間やメンテナンスのしやすさにも注目して、設置の検討を進めていくことが大切です。
自宅の景観を良くしてくれる生垣を設置して、緑に囲まれた豊かな生活を手に入れていきましょう。
【こちらの関連記事もご覧ください】
【外構、造園業者向け】下請脱却!オンライン活用で元請けになる5つのステップを公開
当社が新潟の地方で、オンラインで個人客を集客して、3ヶ月先まで予約で埋めた具体的な方法を記事にしていましたので、ご覧ください。